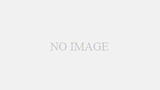神奈川県漢詩連盟会長 香取和之
神奈川県漢詩連盟(神漢連)は平成18年(2006)に、横浜での窪寺啓先生の「漢詩実作教室」の受講生有志が、先生のご指導のもと設立し、早や18年になります。当初は78名でしたが、現在は凡そ230名の会員を擁しています。神漢連は、初代中山清会長に始まり、二代岡崎満義会長、三代三村公二会長と引き継がれ、私が四代目となります。事務局長は、田原健一氏に始まり、桜庭慎吾氏、三村公二氏、高津有二氏と引き継がれ、現在は久川憲四郎氏です。
神漢連の特徴は、以下の三つのキーワードで表わされます。
- 金港方式
二.「漢詩を学ぶ、漢詩で遊ぶ」のモットー
三.多様な人材
第一項は、「神奈川の新様式」として、故石川忠久先生からお褒めの言葉を頂いたものです。
- 毎年、口コミやチラシ、新聞で「漢詩入門講座」の開催PR活動を行い、30~40名の方々が、4月から5月にかけて全5回の「漢詩入門講座」を受講され、古今の名詩を鑑賞すると共に、「だれにでもできる漢詩の作り方」に基づいて七言絶句の作り方を学びます。一首を作成・推敲して卒業詩とします。
- やり方としては、講義と共に、神漢連の幹部会員が総出で数名の少人数グループ毎に実作指導(いわゆる「寺子屋方式」)を行っています。
- 更に、新会員が同期の漢詩サークルを作り、そこに作詩レベルの高い会員を講師として派遣し、作詩の学習を自主的に続けています。現在16のサークルがあります。
第二項のモットー「漢詩を学ぶ、漢詩で遊ぶ」については、以下のように受けとめて推進しています。
- 我々は漢詩を熱心に、且つのびやかにゆったりと学び、そして漢詩を豊かな人生を送るための一助としている。珠玉の詩句への感動、生活のうるおい、描写の妙に触れること、名所旧跡訪問の楽しみ…。
- 漢詩を学ぶ活動のなかに、常に漢詩を楽しみ、遊ぶ要素を取り入れる。「オンライン吟行会」、「自詠自書」、「自詠自吟」…。
大きく捉えれば、ホイジンガーの名著「ホモルーデンス(遊ぶ人)」(ホモサピエンスに対抗する概念)での「遊び」です。また、いわゆる「習破離」の先の「遊び」の境地も目指したいと思っています。
第三項の多様性については、趣味では詩吟や書道の愛好家など、現役時代は民間企業・役所・学校など、いわゆる文科系・理科系、男性・女性、ITに強い人・中国語に堪能な人など…。このような多様性があるので、各漢詩サークルには活気があり、また最近ではZOOMを用いた諸活動や「七絶推敲表」の開発・活用、「神漢連YouTubeチャネル」創出などに繋がっており、「神漢連HP」は充実していると思います。尚、弱点としては、若い会員が少ないことと、漢学・漢詩の正規教育を受けた会員がほとんどいないこと、などです。
尚、神漢連の活動としては、上記の他に「漢詩鑑賞会A,B,C」、「大簡会」、「霧笛女子会」及び「漢詩講演会」などでの漢詩鑑賞、「漢詩研修会」、更に「神辞会」(漢詩へのIT、AI利用の推進。七絶推敲表もその一つ)などを行っています。
このように、神漢連には諸先輩が築き上げたよき伝統があり、それを大切にしながら時代の変化にも対応していきたいと思います。
一方では会員及び講師の高齢化により、組織の新陳代謝の必要性に迫られる場面も多く、例えば漢詩サークルでは「三七八(みなわ)会」のように三つのサークルが合体したものも現れています。また、サークルでの漢詩研修のレベルアップ、若年次のサークル会員による神漢連の主体的活動、IT環境を駆使した運営効率化、若年層への会員勧誘と、課題は尽きませんが着実に進めて行きたいと思っています。
ところで皆様ご存知の通り、「令和6年度全日本漢詩大会神奈川大会」は、2024年10月26日(土)にJR桜木町駅近くの「はまぎんホール ヴィアマーレ」で凡そ350名の全国漢詩愛好家が出席して盛大に開催されました。文部科学大臣賞を始めとする特別賞他の表彰式、受賞詩の吟詠、全日本漢詩連盟会長鷲野正明先生による漢詩講演「蘇州の歴史と漢詩」、構成吟「神奈川を詠う」などのプログラムは概ね好評でした。また26日夜の横浜中華街「菜香新館での交流懇親会」、そして27日の「原三溪園での吟行会」も盛況のうちに終えることが出来ました。これらはひとえに全漢詩連を始めとする各県連の皆様のご協力の賜物です、厚く御礼申し上げます。
論語に「朋あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや」と説かれています。全国の漢詩愛好家と今後ともいろいろと交流できることを楽しみにしております。宜しくお願い申し上げます。