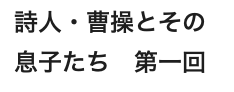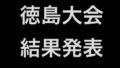全日本漢詩連盟 常務理事 浦上 佳奈
現代の私たちが読んでいる「漢詩」には、およそ3000年ほどの歴史があります。今回のテーマである曹操とその息子たちが生きていた後漢末期から三国時代は、今からおよそ1800年前。その時代にも、当然ながら漢詩は存在していました。
それでは、曹操たちの作った詩とは、いったいどのようなものだったのでしょう?今回は「曹操とその詩」を紹介していきます。
【「人生なんて、はかないものだ」・・・天下人の心】
突然ですが皆さん、ちょっと想像してみてください。「天下を取った人の気持ち」って、どんな風だと思いますか?
天下を取るということは、国でいちばん偉い人になるということです。周りの人が、無条件で自分に頭を下げてくれる。自分の言うことを聞いてくれる。豪邸、ご馳走、財宝、名馬、美女・・・望むものは何でも手に入る。まるで、この世の全てが自分のために存在する、そんな感覚におちいるのではないでしょうか?
実は曹操の後半生は、これに近い状態でした。彼は西暦155年に生まれ、220年に没するのですが、212年に「公」という地位についており、更に216年には「王」になっています。これは、当時の家臣として最高の地位です。
ここで「家臣として」とわざわざ断り書きを入れるのは、家臣の上に絶対的な権力者の「皇帝」が存在するからです。しかし曹操が活躍した後漢王朝の末期は、皇帝の力は衰えてしまってお飾り同然のような扱いとなっていました。お飾りとは言いますが、形式上は皇帝がいちばん偉いので、皇帝に近い者がそのまま実権を握れるわけです。曹操も皇帝を庇護するという名目で自分の手元に置きながら、数々の権力争いや戦に勝ち、国家の頂点へと昇りつめていきます。
そんな曹操は、果たしてどんな詩を書いていたのでしょう?以下は、曹操の読んだ「短歌行」(たんかこう)という詩の一部です。かなり難しい言い回しが出てきますので、本文は飛ばして下部の【訳】だけ読んでもらっても構いません。
對酒當歌 酒に対しては 当に歌うべし、
人生幾何 人生 幾何ぞ。
譬如朝露 譬えば 朝露の如し、
去日苦多 去る日は 苦だ多し。
【訳】
酒を飲むときは、歌って楽しむべきだ。
人生なんて、いったいどれほどのものだろうか。
まるで朝露がおりてすぐ消えるように、はかないではないか。
過ぎ去った日々ばかりが多い。
人生の短さ、人間のはかなさを嘆き、酒を目の前にしたら歌おうじゃないかと言っています。この後はこう続きます。
慨當以慷 慨して 当に以て慷すべし、
憂思難忘 憂思 忘れ難し。
何以解憂 何を以てか 憂を解かん、
惟有杜康 惟だ 杜康有るのみ。
【訳】
そう思うと感情が高ぶってくる、
この忘れがたい憂いを
何によって消し去ったら良かろうか?
ただ、酒あるのみだ。
人生の短さを嘆いていると心が高ぶってきて、胸の底から憂いが湧いてくるといいます。その憂いを晴らすものは酒しかないんだ、飲んで酔っ払って、憂いを忘れようや・・・と歌います。
酒を前にして「人生なんて、はかないものだ」と嘆き、歌う曹操。世の中が乱れに乱れた後漢王朝の末期、ほうぼうで戦が起こり、宮中では血みどろの惨劇が繰り広げられました。曹操自身もそれらの出来事に少なからず関わっています。無数の人の命が砂粒よりも小さく、軽く、あっけなく消し飛んでいった時代、いろいろと思うところがあったのでしょうか。
また、権力争いという大仕事の渦中にいた曹操にとって、人生はたとえ何年あったとしても短く感じられたのかもしれません。この詩の続きでは
「ああ、前途有望な若者よ。君たちのような良き人材を探し出して、客人として迎え、精一杯もてなしたいものだ」
「昔の偉人は、人材の登用にたいそう熱心で、来客があれば食事や風呂を中断してでも応対したという。私もそうあらねば」
などと歌っています。酒を前に嘆きつつも、愚痴をこぼすだけでは終わらず、大きな目標を見据えて確固たる意志を表しているのです。有能な人材であれば身分を問わず採用したと言われる、いかにも曹操らしい詩ですね。
【「吹雪の中、ヒグマがうなり声を」・・・地獄の雪中行軍】
さて、晩年には天下人となる曹操ですが、彼は生まれながらの覇者だったわけではありません。戦に陰謀に、命を脅かされるような目に遭ったことも二度や三度ではなかったのです。
以下の「苦寒行」(くかんこう)という詩は、206年に戦に赴いた際、真冬の太行山脈を越えた時のことを歌ったものだと言われています。かなり長い詩ですので、一部をご紹介します。前に出た「短歌行」同様、本文を飛ばして【訳】だけ読んでも大丈夫です。
北上太行山 北のかた 太行山に上れば、
艱哉何巍巍 艱き哉 何ぞ巍巍たる。
羊腸坂詰屈 羊腸の坂は 詰屈し、
車輪爲之摧 車輪 之が為に摧く。
【訳】
北上して、太行山脈を越えようとすれば、
山はなんと高く聳え立っていることか。
羊腸の坂は曲がりくねって険しく、
戦車の車輪も砕けてしまうほどだ。
冬山の雪中行軍は、現代でも大変厳しいものです。ましてや1800年前、方位磁石もGPSも無かった時代、険しい山道は、天ではなく地獄へと続いているように感じられたでしょう。詩の続きはこうです。
樹木何蕭瑟 樹木 何ぞ蕭瑟たる、
北風聲正悲 北風 声 正に悲し。
熊羆對我蹲 熊羆 我に対して蹲り、
虎豹夾路啼 虎豹 路を夾んで啼く。
【訳】
ものさびしく立ち並ぶ木々に、
北風が悲しい音を立てて吹きつける。
熊やヒグマが私に対してうずくまり、
虎や豹は道の両側でうなり声を上げる。
険しい山道を行く曹操に追い打ちをかけるかのように、北風が吹きつけます。更に熊やヒグマがうずくまってこちらをうかがい、虎や豹があちこちでうなり声を上げています。今にも飛びかかってきそうな猛獣たち。何たる恐怖!それでも、前に進まなくてはなりません。詩は更に続きます。
谿谷少人民 谿谷 人民少なく、
雪落何霏霏 雪 落つること 何ぞ霏霏たる。
延頸長歎息 頸を延ばして 長歎息し、
遠行多所懷 遠行して 懐う所多し。
【訳】
谷あいには住人も少なく、
雪がしきりに降り続ける。
首を伸ばして長い溜息をもらし、
旅路の長さ、遠さを振り返ると、胸には様々な思いが生じる。
この後も、詩は続きます。谷川を渡りたいのに橋が見当たらず、さまよううちに暮れ方になり、人も馬も飢えてきて、帰りたい思いに駆られます。それでも薪を取り、火を起こし、氷を溶かして粥を作り、何とか飢えをしのぐのでした。
この詩では全体を通して、雪降りしきる冬の山道を進む軍隊の様子や、悪天候や猛獣に苦しめられる人々の心情が大変リアルに描かれています。死と隣り合わせの恐怖の中でも、冷静に、客観的に物事を見据える曹操の眼力や胆力がうかがい知れます。
▼「身は老いても、心は若く」・・・晩年の人生観
こんな風に、苦労に苦労を重ねた甲斐あって、曹操は晩年、「公」や「王」といった地位を手にします。さぞご満悦・・・かと思いきや、彼は「歩出夏門行」(ほしゅつかもんこう)という詩の中で、晩年の心情をこんな風に歌っています。
神龜雖壽 神亀 寿と雖も、
猶有竟時 猶お 竟くる時有り。
騰蛇乘霧 騰蛇 霧に乗ずるも、
終爲土灰 終には 土灰と為る。
【訳】
亀は、長寿でめでたい生き物と言われるが、
それでもいつか、命尽きて死んでしまう。
霧に乗じて天を翔けるという蛇も、
やがて地に落ちて死んでしまい、土や灰と化してしまう。
長寿を誇る亀や神聖な蛇も、死からは逃れられないと言います。もちろん、人間も例外ではあ
りませんが・・・
老驥伏櫪 老驥 櫪に伏するも、
志在千里 志は 千里に在り。
烈士暮年 烈士 暮年、
壮心不已 壮心 已まず。
【訳】
しかし名馬は、年を取って馬小屋の飼い葉桶の前に伏していても、
その志は、若い時と同じように、千里の彼方を駆けめぐっている。
このように、勇猛果敢なますらおは、たとえ晩年になっても、
若い時の心を忘れたりはしないのだ。
曹操は、たとえ身は老いたとしても、若かりし頃の志は忘れていないぞ、と自分に言い聞かせ
るように歌います。そして、こんな言葉で詩を締めくくるのです。
盈縮之期 盈縮の期は、
不但在天 但だ 天にあるのみならず。
養怡之福 養怡の福は、
可得永年 永年を得べし。
幸甚至哉 幸甚 至れる哉、
歌以詠志 歌いて 以て 志を詠ぜん。
【訳】
寿命の長短は、
天が決めるだけではない。
身体をいたわり、心を明るく保てば、
きっと長寿を得られよう。
ああ、まことに幸いなるかな、
この思いを歌に託して詠じよう。
先の「短歌行」では、人間のはかなさを嘆いていてやや悲観的な面もありましたが、この詩で
は人生の長短を決めるのは天だけではないと述べたうえで、人の意志は天の定めた寿命をも
超えられるのだと、力強く宣言します。
今回紹介した詩は、1800年前の異国の天下人が詠んだものです。しかし、現代を生きる我々
の価値観や死生観にも、どこか通じるものがあります。。
時代や国境を越えて、人の心を揺さぶる言葉を紡ぎ、歌に乗せて高らかに詠じたであろう曹
操。その姿はまさに一世の英雄であり、詩人でもありました。
次回は、曹操の息子であり、魏王朝の初代皇帝でもある「曹丕」についてお話します。
<参考書籍>
伊藤正文注 「曹植」 岩波書店
松枝茂雄編 「中国名詩選」 岩波文庫
川合康三編訳 「曹操・曹丕・曹植詩文選」 岩波文庫
趙幼文校注 「曹植集校注」 中華書局
(令和7年(2025)10月29日 公開)
全日本漢詩連盟のホームページでは、このテーマについて6回にわたり連載していきます。
令和7年10月29日の時点で6回分の原稿を書き終えており、これから刊行される書籍等からの影響は受けていません。